なんか久しぶりだな…と思ったら1月以来の月イチディスクレビュー。もはや月イチでもなんでもないですね…とはいえ今年はニュース掲載の相談をもらったり、インタビューさせてもらったりのほか、昔の縁で他媒体でライブレポートを書かせてもらったりしてたので、まぁいろいろやってたっちゃやってました。
今年ももう後半ですが、取材したいなという案件もいくつかあるので、また随時ですね。というわけでいってみましょう。
■MALEVOLENCE『WHERE ONLY THE TRUTH IS SPOKEN』
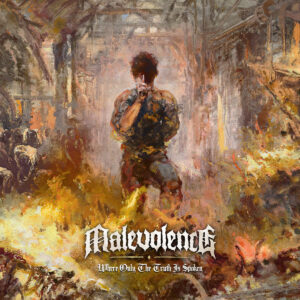
UK、ヨークシャー出身のメタルバンドの4作目。バンド名も、2022年に出た前作がわりと話題になっていたことも知っていたんですが、正直あんまりピンと来ていなかったんですよね。ただこれはだいぶアタリのアルバムです。
サウンド的にはPANTERA~LAMB OF GODの流れを汲んだスタイル。ハードコアの要素もたっぷり(初期はビートダウン的な側面も強かった)ながら、メタルコアともちょっと違う感覚で、グルーヴメタルと言ったほうがしっくりくるような気がします。で、今回はそこにサザンロック的というか、ブルース流れの渋みを大量添加。もちろん以前からそういった雰囲気はあったものの、多少参考にする程度だったのが、今回はもっと露骨に匂ってきます。それが初期のビートダウン要素と相まって、グルーヴ感をマシマシに強調することに成功。ヴォーカルももともと非人間的なデスヴォイスで押すタイプではなく、わりとナチュラルなわめき声が特徴だったんですが、わめきつつそのままメロディを追う様も見せるようになっています。まぁやっていることは後期PANTERAとかCROWBARみたいな感じと言っちゃえばそこまでなんですが、単なる真似に終わらずに、今様なモダンさやヨーロッパ的な湿り気をしっかり反映したアレンジセンスが光っています。
2019年に来日しているんですが、今ではメタルのフィールドで大物のサポートにも抜擢されているので、おいそれと再来日はできなさそうな感じ。むしろ今の状態で観たいんですけどね。ちょっと大きめのイベントに出るとかで来てくれることに期待したいです。
■View From The Soyuz『Ubiquitous』
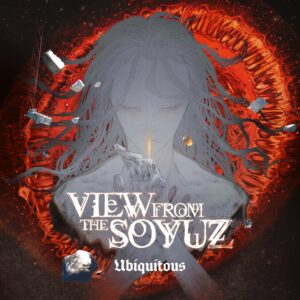
東京のハードコア・バンドの1st。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いという言葉がピッタリというか、尋常じゃないレベルで話題を集め、メジャーフィールドにも切り込んでいるバンドです。過去にリリースしたEP等では初期型のメタルコアというかエッジメタルを思わせるスタイルでしたが、今回もそれを踏襲しつつ、さらにアップデートがなされています。
まずもって聴いて驚くのが、音の整合感。以前からあったメロデス的なアプローチだけでなく、ブラックメタル風味やクリーンな歌メロも導入したり、数名のゲストヴォーカルを招いたり…と要素を拡大してスケール感を増しつつも、曲の展開は滑らかだし、冗長にならずパキっとまとめられています。細かく刻まれるリフはいちいち口ずさめるほどの歌心があるし、根本的にキャッチーなんですよね。同時にハードコア・シーンに軸足を置きながらのし上がってきたこともあってか、ハードコアへの解像度がより高まっており、正しく「メタル×ハードコア」という意味で強さとともに、ドラマ性もたっぷりの仕上がり。どれも取ってつけたような感じはなく、元々持っていたものを計算しながら開陳したんだろうと思えるし、まだほかの手の内も残っていそうな感じがします。
出演するフェスやイベントの規模が大きくなる中、本人たちの意識がどう変化したかはわからないですが、変にコマーシャルにならず「この音でどこまでいけるか」みたいな気概はものすごく伝わってきます。そのあたりはハードコアらしい頑固さが垣間見えるし、これが売れればシーンにとってもメリットしかないと思います。素直なかっこよさに感嘆するだけでなく、10代とは言わなくとも、せめて20代前半に出会いたかったバンドでありアルバムです。
■ANTHONY GREEN『SO LONG, AVALON』
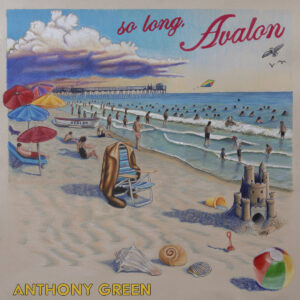
SAOSIN、CIRCA SURVIVEほか、近年ではL.S.DUNES等でも知られるアンソニー・グリーン(vo)のソロアルバム。純粋なオリジナル作ではなく、2008年のソロデビュー作『AVALON』を再構築したアルバム…だそう。
たしかにオリジナル版と聴き比べてみると、単に再録したのではなく、けっこうアレンジに手が加えられています。さすがに別の曲に聴こえるほどの再構築こそしていないものの、メロディと歌声(声はほとんど変化していないです)はそのままに、音の重ね方や用いる楽器を変えることで、かなり印象が違って感じられるようになっています。こうして聴いてみると、オリジナル版はアコギ主体の場面が多く素朴なんですよね。ちょっとフォークっぽさが漂う場面もあるのに対し、今回の再構築版は空間系のエフェクトで彩ったギターを多く用いる等で、全体的にアトモスフェリックさをプラス。そのうえでミックス上ヴォーカルの音量が上がっているようにも感じられます(聴く環境のせいかもしれないけど)。よくある「アルバムが完成してリリースした後で、あそこをもっとこうすればよかったと思った」みたいなのがきっかけかはわからないですが、キャリアを重ねたことで変わったことと変わっていないことがよくわかるし、何より原曲のよさは損なわれていないので、オリジナル版が好きな人はもちろん、これがアンソニーのソロ初体験の人にもいいかもしれないですね。
ちなみにアンソニー、いつもバンドを出たり入ったりしているのでいまいち動向がわかりにくいんですが、とりあえずSAOSINには不参加。L.S.DUNEは11月にライヴの予定あり。THE SOUND OF ANIMALS FIGHTINGもツアーに参加予定。あとはそんなにアクティブではなさそうですが、FUCKIN WHATEVERというプロジェクトにも参加しているそう。知らないうちに何かリリースされていたりするので、ちょこちょこチェックしておきましょう。
■VILDHJARTA『Dar skogen sjunger under evighetens granar』

スウェーデンのプログレッシヴ・メタルバンドの3作目。2月に来日したHUMANITY’S LAST BREATHのバスター・オデホルム(g)がドラムを担当しているバンドです。ただでさえバンド名から読みにくいのにこのタイトルは何事かと思ったら、スウェーデン語で直訳すると「Where the forest sings under the eternal spruce trees(永遠のトウヒの木々の下で森が歌う場所)」になるそう。
言葉を選ばずに言えば、MESHUGGAHに端を発しつつ独自進化したDjent~Thallの中でもひと際クセのあるバンドですが、今回はこれまで以上の不気味さと複雑怪奇さ。息が長く、アクセントの位置が一貫しない不協和音まみれのリフで不安を煽ったかと思えば、急にクリーンで幻想的な場面が急に顔を出してきて、展開を把握することはほぼ不可能。歌詞も全編スウェーデン語らしく、宗教画を思わせるアートワークと相まってさらにミステリアスというか、理解を越えた化物を見るような感覚さえ覚えます。なのに身を任せると気持ちよくなってくる。もちろん音楽としてカテゴライズするとメタルの一種だけど、メタルの聴き心地じゃないんですよね。むしろ細部まで偏執的なまでに統制された音は聴けば聴くほど静謐で、美しいとさえ思えてきます。ほかではなかなかない、聴くというより体験する、と言った方がよさそうなアルバムです。
本作リリース前にギタリストが脱退したので、現在3人編成ではありますが、ライヴってできるんですかね(MVでは一応演奏シーンが使われている)。ツアー自体も10年くらい前に1度やったのみだそうで、むしろ再現性を一切考えずに作っているから、この境地に到達できるのかも?
<LINK>
MALEVOLENCE:https://x.com/MalevolenceRiff
View From The Soyuz:https://x.com/vfts_freehill
ANTHONY GREEN:https://www.anthonygreenmusic.com/
VILDHJARTA:https://www.instagram.com/vildhjartaofficial

